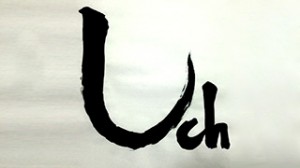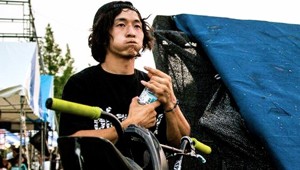栗村修「踏切事件」
先日開催された『パリ~ルーペ』で起こった『踏切事件』に関する議論が地味に続いています。
『自転車ロードレースと踏切』というのは、これまで歴史という名の『大正義』が議論の発生を抑え込み、ある意味で問題全体をスルーさせてきた、若干大袈裟な表現かもしれませんか『自転車ロードレース界のタブー』の一つでした。
それは、お酒やタバコといった、明らかに体に害があり、死亡リスクを上げる嗜好品が、歴史という名の大正義のもと、世の中に受け入れられ続けていることにも若干似ている気がします。
もし、お酒やタバコがこれまでの時代に一切存在せず、今の時代に急に姿を現したならば、恐らく『ドラッグ』と同等の扱いを受けることになるでしょう。
『踏切』も同様で、世界186カ国で放送され数百万人が視聴する公道型プロスポーツイベントが新たに企画されるとして、勝敗を左右しつつ大参事に繋がる恐れのあるこの懸案事項の『踏切』を、現行のルール(電車は止めることなく通常通り運行させ遮断機が閉まった時は自己判断で止まりなさい)と同様の形で設定するとは到底考えられません(更に選手たちにとってはこのレースに勝てば人生が変わるようなステイタス性がある)。
これまでも、踏切の存在がレース結果に影響を与え、様々な物語を創り上げてきた数多くの歴史があります。
しかし、今回の様に、鉄道会社が遺憾の意を表明し、UCIが調査に乗り出し、そして、選手(パオリー二)が非公式ながら声明文(これだけの大規模なプロスポーツイベントを開催するならば電車を止めるべき)を公表するような展開に発展したことはありませんでした。
これも、自転車ロードレースという、ヨーロッパの『ガラパゴススポーツ』が、ようやく世の中の常識という波に晒されはじめていることを示す兆候なのかもしれません。良く言えば、本当の意味で『ワールドワイドなメジャースポーツ』へのスタート地点に近づきつつある兆しともとれます。
ただ、よくよく考えてみると、自転車ロードレースには、他にも無茶苦茶な『オリジナル常識』が数多く残っています。
そこが自転車ロードレースの魅力である一方で、同時にこのスポーツの拡大を抑制している要素であるということを、中にどっぷり浸かってしまっている関係者たちは認識しなければならないのでしょう。